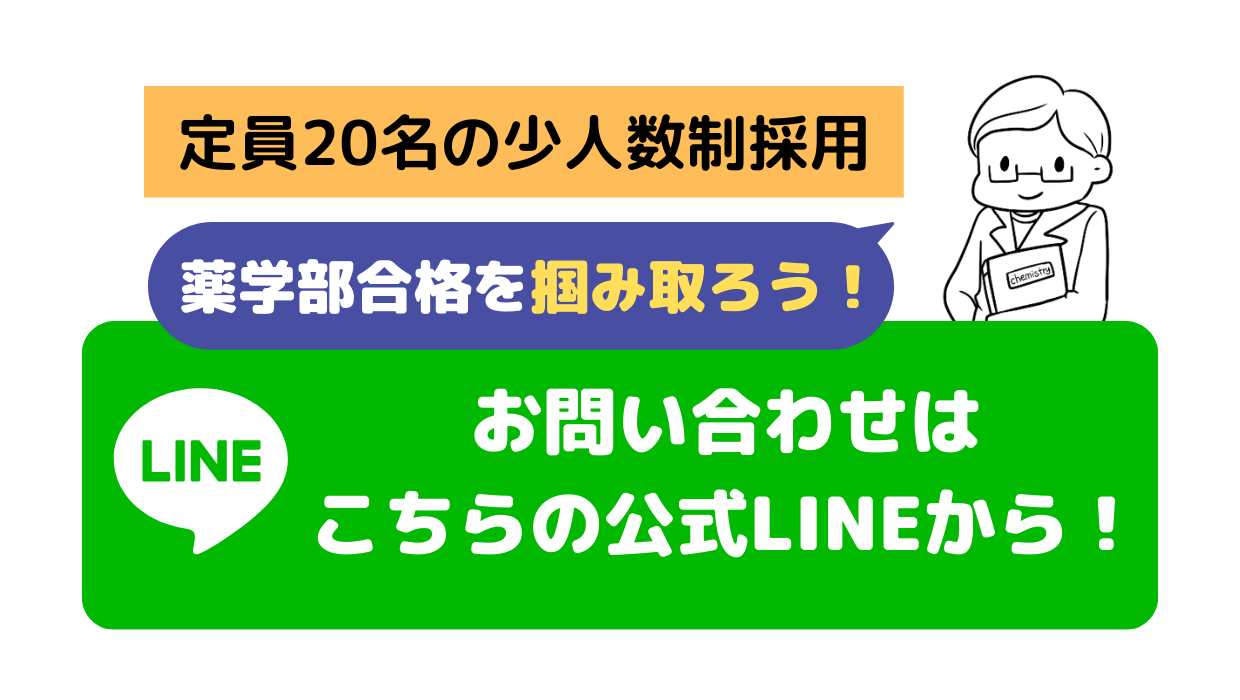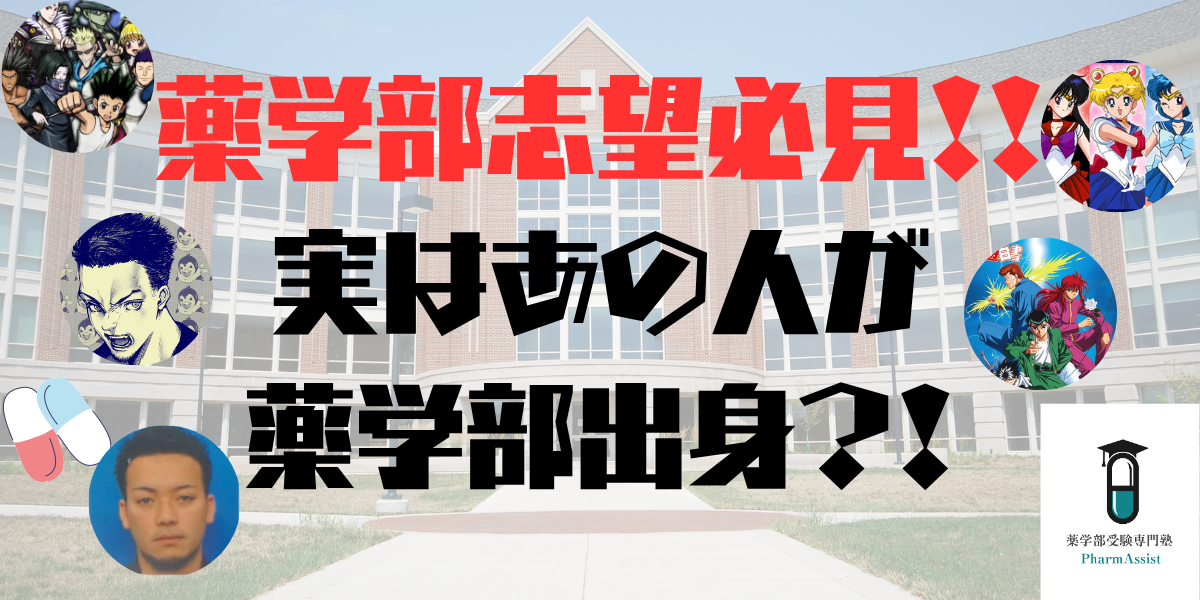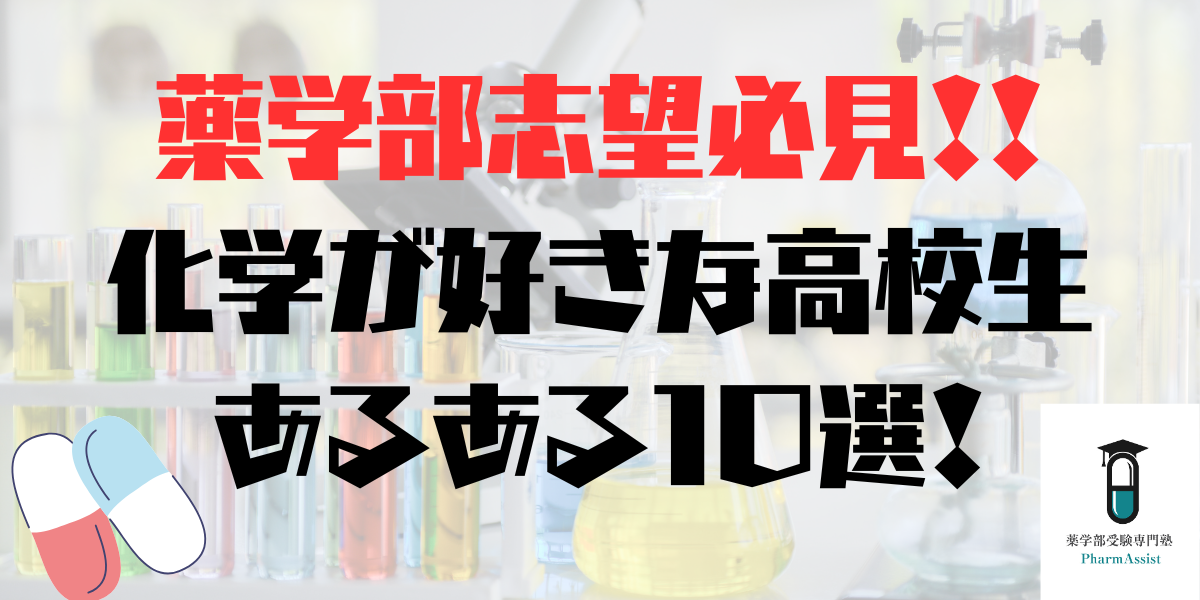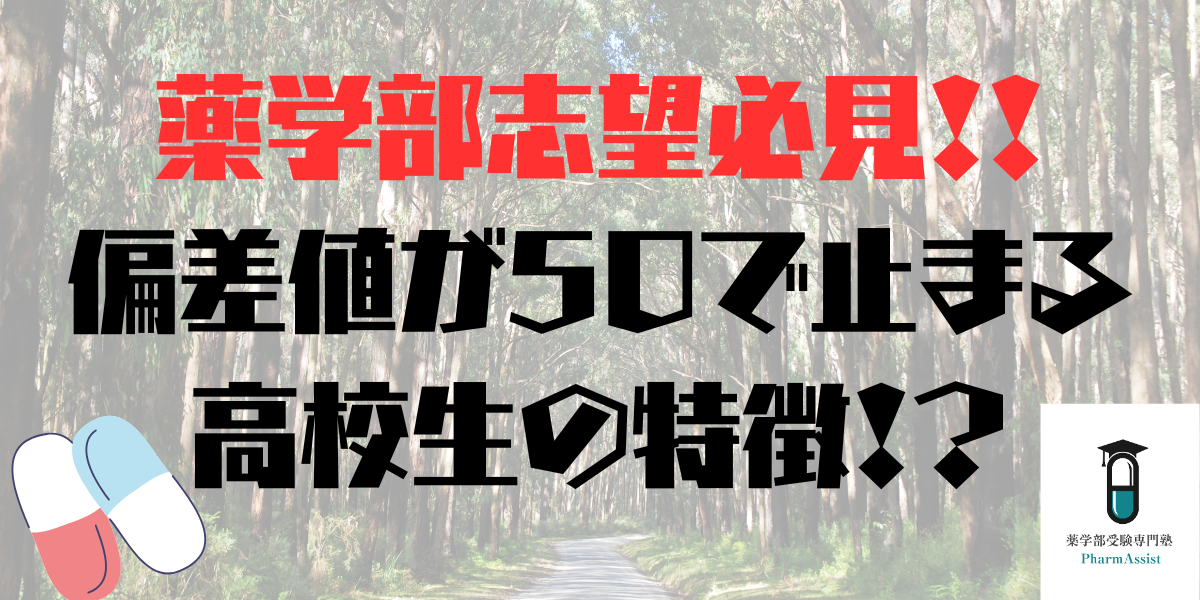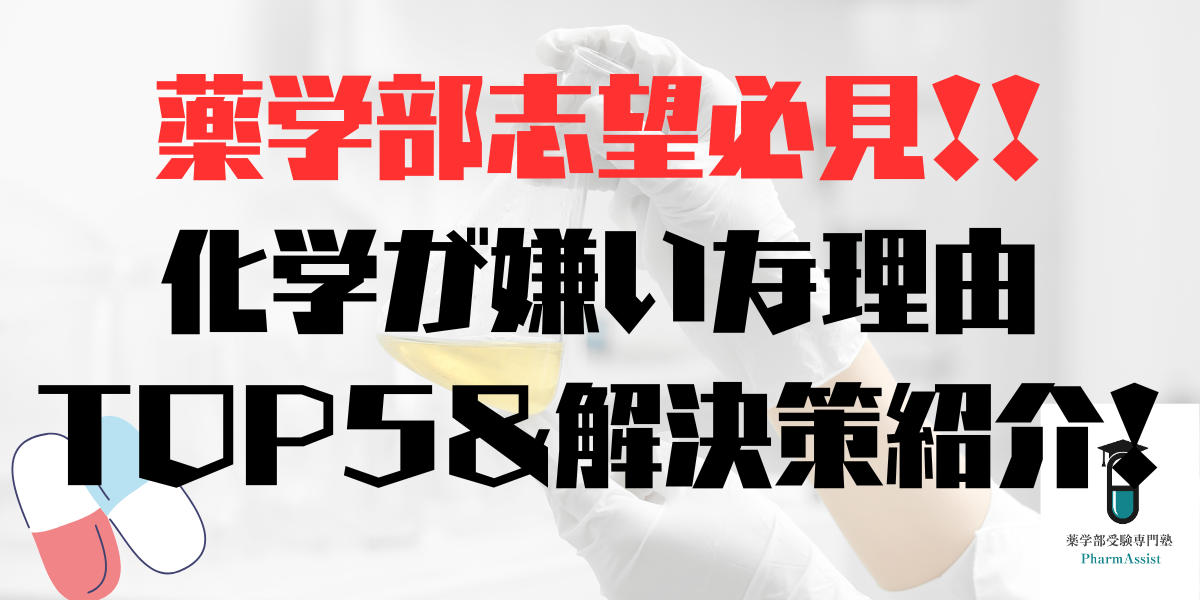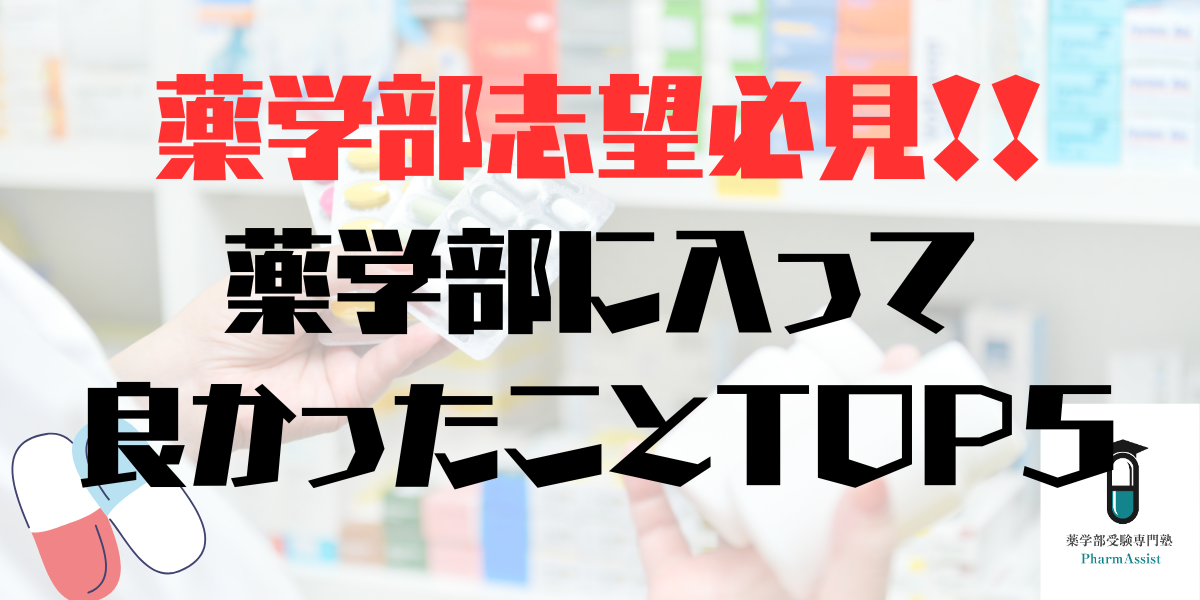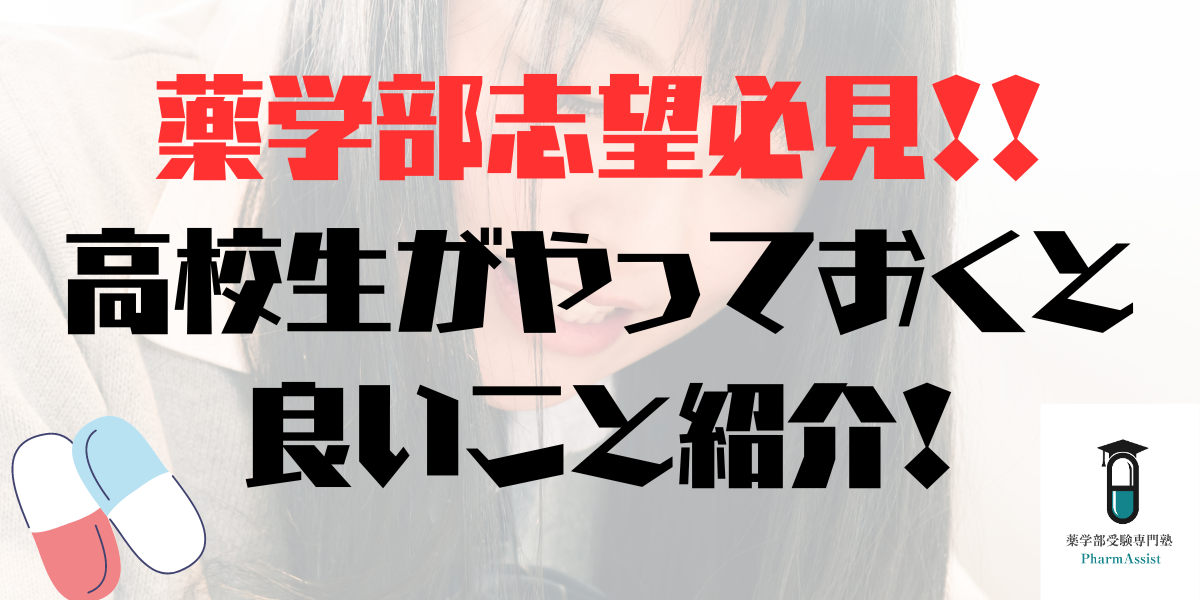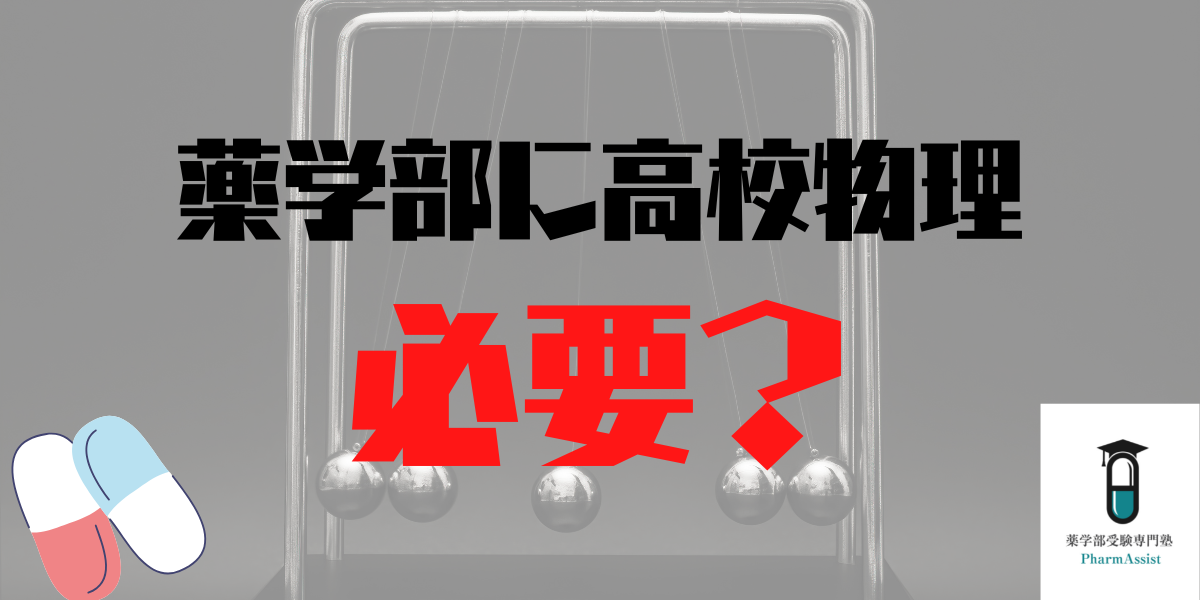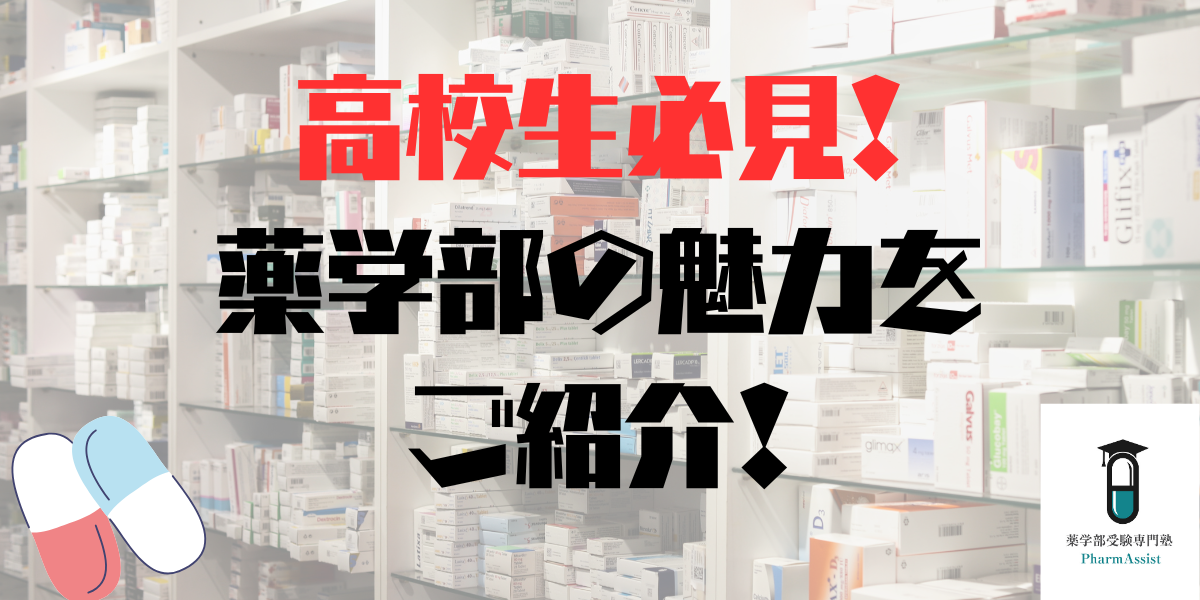【完全版】 東京理科大学薬学部 を徹底解剖!偏差値から入試対策、キャンパスライフまで高校生必見の情報満載!【2025年最新版】
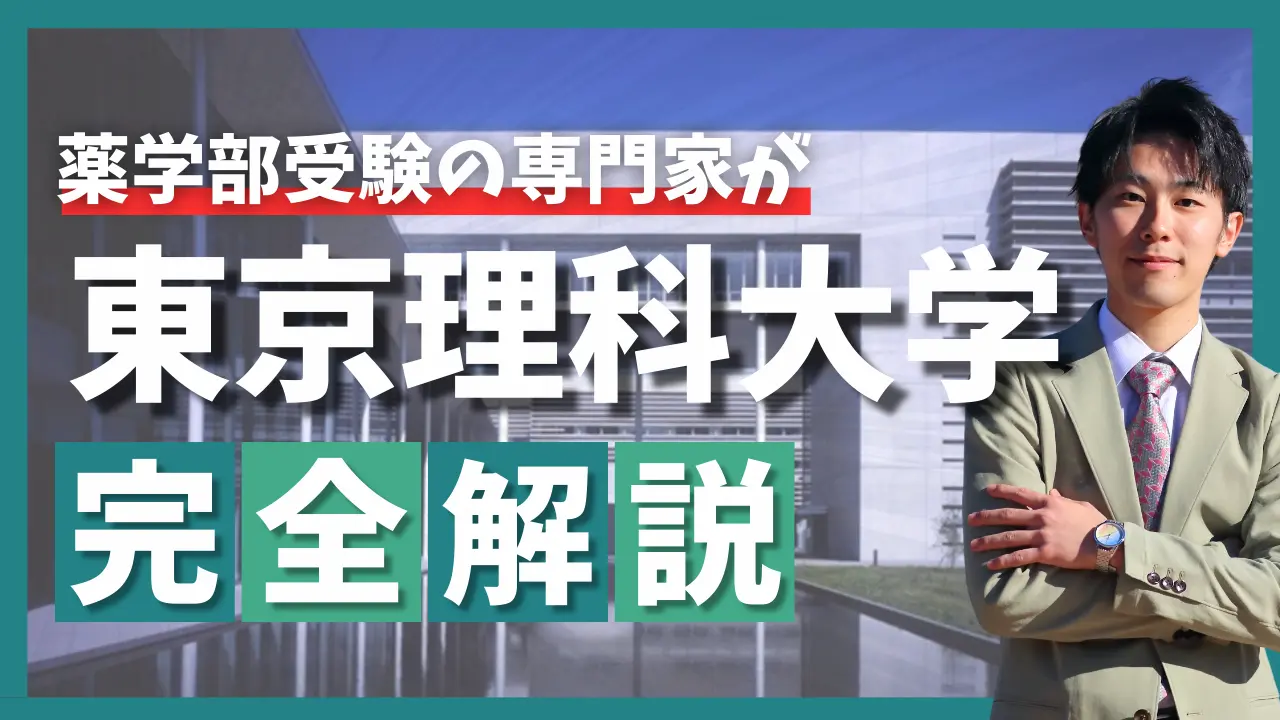
東京理科大学薬学部 を志望する高校生の皆さん、こんにちは!
皆さんは、日本の科学技術を牽引し、多くのノーベル賞受賞者を輩出してきた東京理科大学に、薬学部があることをご存知でしょうか?
このブログ記事では、東京理科大学薬学部の魅力や特徴、そして皆さんが受験に向けて知っておくべきあらゆる情報を、徹底的に深掘りしていきます。
偏差値や学費から、入試科目ごとの傾向と対策、さらには卒業後の進路まで、皆さんの疑問をすべて解決できるよう、1万字を超えるボリュームで詳しく解説していきますので、ぜひ最後まで読んで、志望校選びや受験対策に役立ててください!
以前の投稿では、岐阜薬科大学について徹底解説をしている記事を作成しています!
薬学部志望の高校生、岐阜薬科大学志望の受験生はぜひ、こちらからご覧ください!
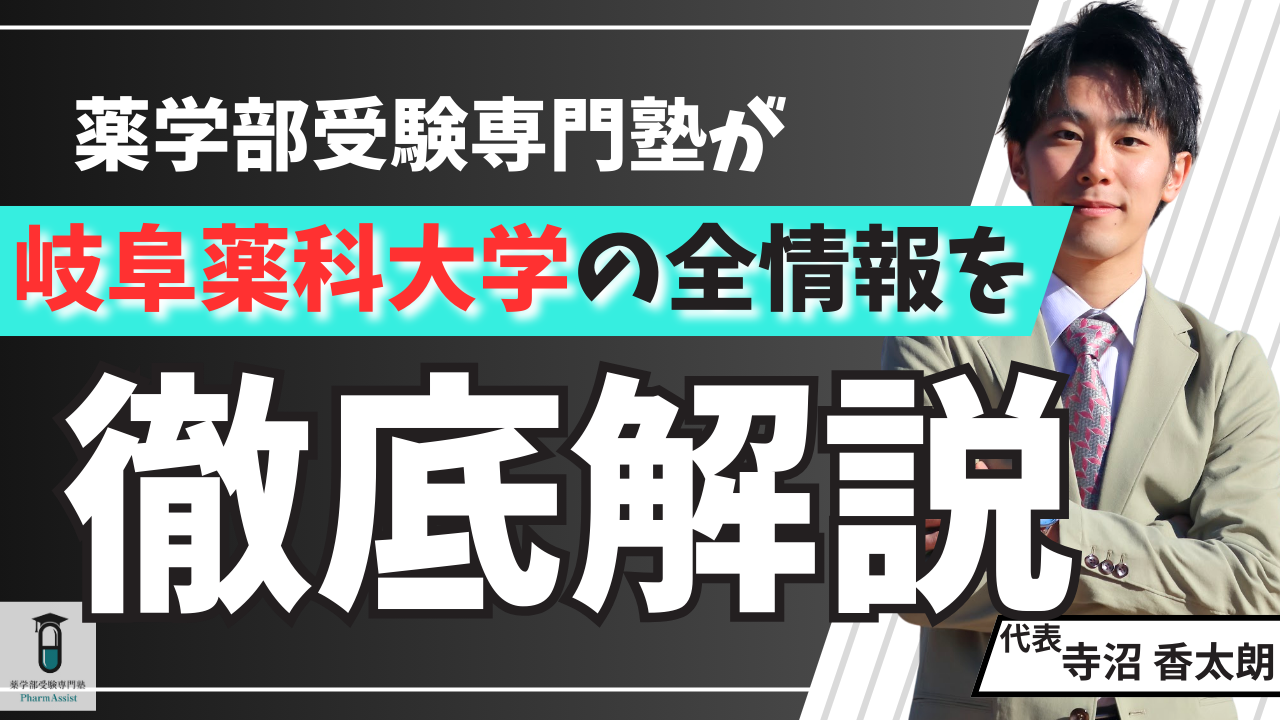
東京理科大学薬学部とは?未来の医療を担う人材を育成する学び舎
東京理科大学薬学部は、豊かな知性と人間性を備え、未来の薬学を担う人材を育成することを目指しています。
概要と歴史
東京理科大学は、1881年(明治14年)に「理学の普及を以て国運発展の基礎とする」という建学の精神を掲げ、東京物理学講習所(後の東京物理学校)を主な前身として設立されました。
その後、1949年に東京理科大学が設置され、理学部第一部と理学部第二部が設立されました。
薬学部は、1960年(昭和35年)4月に神楽坂校舎に設置された、同大学で3番目の学部です。
薬学教育制度の変遷に伴い、2006年(平成18年)4月には薬学教育6年制移行により、薬学部薬学科(6年制)と生命創薬科学科(4年制)が新設されました。
2011年(平成23年)3月には薬学部薬学科(4年制)と製薬学科は廃止されています。
2つの学科:薬学科(6年制)と生命創薬科学科(4年制)
東京理科大学薬学部には、目的の異なる2つの学科が設置されています。
- 薬学科(6年制課程)
- 目指す人材像: 薬学科は、薬の性質と作用、薬物治療、医薬品の適正使用、公衆衛生といった薬剤師の職能の基盤となる専門的知識と関連する技能、態度を習得し、医療・公衆衛生における実践能力と問題解決能力を身につけることを目指しています。さらに、問題を研究に結びつけることのできる能力も兼ね備えた薬剤師の育成を目指しています。
- 教育内容: 徹底した基礎教育と薬学専門教育を行い、充実した施設と医療機関との連携による実践的な薬剤師職能教育が特徴です。
- 生命創薬科学科(4年制課程)
- 目指す人材像: 生命創薬科学科は、高度な専門知識と技能を備え、世界をリードできる優れた薬学研究者の養成を目指しています。
- 特徴: 定員100名の薬学系4年制学科は、国内で唯一です。東京理科大学の実力主義は本学科でも継承されています。
- 研究分野: 従来の手法に加え、ゲノム情報などの理論的なアプローチを取り入れて新薬を創る「創薬科学」と、生命の営みを多角的に学び、病気が起こるメカニズムを明らかにして、より優れた薬を開発する「生命薬学」の2分野で研究活動が行われています。
男女比率
2024年の新入生における男女比率は、**男子39%、女子61%**と、女子学生の割合が比較的高いことが特徴です。
強みと特徴:実力主義と共同研究
東京理科大学は、「実力主義」を教育の柱としています。薬学部においても、この実力主義は継承されており、学生一人ひとりが高い専門性と実践力を身につけられるよう、厳しくも質の高い教育が提供されています。
また、東京理科大学薬学部は、大学内の他学部学科だけでなく、国内外の様々な医療系大学や研究機関、企業、官公庁と協働・連携して社会に貢献しています。お互いの専門分野を活かした異分野連携研究・教育を推進しており、これにより学生は多様な視点と実践的な学びの機会を得ることができます。
薬学部のキャンパス情報:2025年移転でより学びやすく!
東京理科大学薬学部は、2025年度から主要なキャンパスが変更になります。
葛飾キャンパスへの移転
これまで薬学部は野田キャンパス(千葉県野田市)に所在していましたが、2025年4月に薬学部(薬学科および生命創薬科学科)と薬学研究科が野田キャンパスから葛飾キャンパス(東京都葛飾区)へ移転する予定です。この移転により、都心からのアクセスが向上し、より充実した学生生活が期待されます。
各キャンパスの所在地とアクセス
東京理科大学には複数のキャンパスがあり、薬学部以外にも以下のキャンパスが存在します。
- 神楽坂キャンパス神楽坂校舎 (本部/理学部第一部/理学部第二部)
- 〒162-8601 東京都新宿区神楽坂1丁目3
- アクセス:JR総武線、地下鉄有楽町線・東西線・南北線・大江戸線飯田橋駅下車、徒歩5分
- 神楽坂キャンパス富士見校舎 (経営学部〈国際デザイン経営学科のみ2~4年次〉)
- 〒102-0071 東京都千代田区富士見1丁目11の2
- アクセス:地下鉄半蔵門線・東西線・新宿線九段下駅下車、徒歩8分、または飯田橋駅下車、徒歩10分
- 葛飾キャンパス (工学部/薬学部/先進工学部)
- 〒125-8585 東京都葛飾区新宿6丁目3の1
- アクセス:JR常磐線・地下鉄千代田線金町駅、京成金町線京成金町駅下車、徒歩8分
- 2025年からは薬学部がここに加わります。
- 野田キャンパス (創域理工学部)
- 〒278-8510 千葉県野田市山崎2641
- アクセス:東武野田線運河駅下車、徒歩5分
- 北海道・長万部キャンパス (経営学部〈国際デザイン経営学科・1年次〉)
- 〒049-3514 北海道山越郡長万部町字富野102の1
- アクセス:JR函館本線・室蘭本線長万部駅下車、徒歩20~25分・車5分
オープンキャンパスは、葛飾キャンパスで2025年5月25日(薬学部、工学部、先進工学部対象)に開催されます。また、夏のオープンキャンパスも2025年8月10日に葛飾キャンパス(薬学部、工学部、先進工学部対象)で行われる予定です。いずれも事前予約が必要です。
東京理科大学薬学部の「今」を知る!気になるデータ徹底解説
受験を考える上で、偏差値や倍率、学費といった具体的なデータは非常に重要です。ここでは、東京理科大学薬学部の最新情報を詳しく見ていきましょう。
偏差値と共通テスト得点率(ボーダーライン)
東京理科大学全体の偏差値は42.5~62.5です。薬学部の偏差値は60.0とされており、比較的高い水準にあります。
共通テスト利用入試における得点率(ボーダーライン)は以下の通りです。
- 薬学科
- A方式4教科型(共テ利用):84%
- A方式3教科型(共テ利用):85%
- A方式2教科英(共テ利用):86%
- 生命創薬科学科
- A方式4教科型(共テ利用):84%
- A方式3教科型(共テ利用):85%
- A方式2教科英(共テ利用):86%
入試倍率
2024年度入試における薬学部の倍率は以下の通りです。
- 薬学部 一般選抜合計: 2.9倍 (2023年度: 3.0倍)
- 募集人員140名、志願者数3,317名、受験者数3,096名、合格者数1,060名
- 薬学部 共テ合計: 3.1倍 (2023年度: 2.9倍)
- 募集人員50名、志願者数1,515名、受験者数1,422名、合格者数455名
各学科・方式ごとの倍率は以下の通りです。
- 薬学科
- 一般B方式: 2.9倍 (募集人員40名、志願者数964名、合格者数310名)
- グローバル方式: 4.8倍 (募集人員5名、志願者数83名、合格者数15名)
- 共テA方式: 3.1倍 (募集人員15名、志願者数768名、合格者数246名)
- 共テC方式併用: 4.4倍 (募集人員10名、志願者数198名、合格者数34名)
- 公募制: 3.3倍 (募集人員10名、志願者数20名、合格者数6名)
- 生命創薬科学科
- 一般B方式: 2.4倍 (募集人員40名、志願者数689名、合格者数267名)
- グローバル方式: 4.5倍 (募集人員5名、志願者数66名、合格者数13名)
- 共テA方式: 2.7倍 (募集人員15名、志願者数381名、合格者数140名)
- 共テC方式併用: 3.5倍 (募集人員10名、志願者数168名、合格者数35名)
- 公募制: 1.5倍 (募集人員10名、志願者数6名、合格者数4名)
学費の詳細
2025年度入学者の初年度納入金額は以下の通りです。
- 薬学科: 2,497,740円
- 入学時最小限納入金額: 1,420,240円
- 内訳: 入学金300,000円、授業料1,605,000円、施設費550,000円、諸会費42,740円
- 生命創薬科学科: 2,052,740円
- 入学時最小限納入金額: 1,197,740円
- 内訳: 入学金300,000円、授業料1,160,000円、施設費550,000円、諸会費42,740円
その他、薬学科の長期実務実習費は履修時に一部別途徴収される場合があります。卒業研究費や選択科目実験実習費も履修に応じて別途徴収されることがあります。学費は2段/延納で納入可能です。
薬剤師国家試験合格率
2024年薬剤師国家試験の新卒合格率は**90.28%**です。過去5年間の合格状況も公表されています。
東京理科大学薬学部の入試を徹底攻略!傾向と対策
東京理科大学薬学部の入試は、多様な方式が用意されており、併願もしやすい設計になっています。各入試方式の特徴と、具体的な科目別の傾向・対策を見ていきましょう。
一般選抜の入試方式
東京理科大学の一般選抜には、大きく分けて大学入学共通テストを利用する「A方式」と、大学独自の試験を行う「B方式」「S方式」があります。
- A方式(大学入学共通テスト利用)
- 4教科型: 国公立大学も受験する人におすすめです。国公立大学受験用に勉強した共通テスト対策を活かせるため、併願しやすい方式です。出願は1学科までとなります。
- 3教科型: 得意科目を活かして受験したい人におすすめです。他の私立大学の共通テスト利用型入試との併願もしやすく、2学科まで出願可能です。
- 2教科+英語資格検定: 英語を事前にしっかり対策しておきたい人におすすめです。外部英語資格・検定試験のスコアが基準を満たせば出願でき、他の受験科目の勉強に集中することができます。こちらも2学科まで出願可能です。
- 理学部第二部(夜間学部): 夜間学部を志願する人向けの方式です。夜間学部の中から1学科のみ出願可能ですが、異なるA方式(4教科型、3教科型、2教科+英語資格検定)との併願も可能です。
- B方式(大学独自の入学試験)
- 全学部で実施され、学部ごとに異なる日程で併願チャンスが広がります。
- 昼間学部は、本学キャンパスのほか、全国6会場(札幌、仙台、名古屋、大阪、広島、福岡)でも実施されます。日程を組み合わせることで、最大8学部の出願が可能となり、チャンスが広がります。
- S方式(専門コース)
- 創域理工学部数理科学科、電気電子情報工学科の専門コースを対象に実施されます。出願時に希望する専門コースの系を選択します。試験日が重複しなければB方式との併願も可能です。
併願のポイント
東京理科大学では、様々な入試方式を組み合わせて併願することで、合格のチャンスを広げることができます。
- A方式とB方式、S方式は自由に併願が可能です。
- B方式とS方式は、異なる入試日程であれば自由に併願が可能です。
- A方式内では最大2学科まで併願可能です。
- B方式、S方式では、異なる入試日程であれば自由に併願可能です。
- 同一日程で受験科目が同じであれば、2学科まで併願が可能です。ただし、同一試験日の創域情報学部と創域理工学部、またはB方式とS方式の併願は不可とされています。
総合型選抜
東京理科大学では、総合型選抜(英語資格検定+特定教科評価)を実施しています。薬学部では、薬学科と生命創薬科学科で募集が行われます。
- 募集人数: 各学科8名
- 出願期間: 10月27日~11月1日
- 選考日: 11月16日
- 合格発表: 12月12日
- 選考方法: 書類審査、面接、小論文などが課されます。
- 出願条件: 現役生のみ出願可能で、成績等の条件があります。
入試科目・配点・傾向・対策
薬学部の一般選抜(B方式)の個別学力試験では、数学、理科(化学)、外国語(英語)の3教科が課され、合計300点満点です。グローバル方式では、数学と理科(化学)の2教科と英語資格が出願資格・加点となります。共通テスト利用のA方式、C方式では、個別学力試験は課されません。
以下に、主要3科目の傾向と対策を詳しく解説します。
英語
- 傾向:
- 大問2~3題構成で、試験時間は60分。全問マークシート方式で、設問文も全て英語です。
- 近年、読解・会話文問題のみの場合や、読解問題のみの場合の他、文法・語彙問題が加わることもあります。
- 2025年度は読解英文の語数が2024年度の約2倍と大幅に増加しました。
- 読解問題では、語彙の同意表現や英文の内容の言い換えを問う問題が多いです。
- 難しい語句も出題されますが、前後の内容から意味を類推できるものが多い傾向にあります。
- 文法・語彙問題は標準的なものが多く、頻出問題に慣れておくことが重要です。
- 出題英文の難易度が若干高くなっており、1文が長い英文も多く、文法的に正確に解釈できないと読み間違える可能性があります。
- 設問自体は総じて標準的で、答えに迷うものは少ないです。
- 試験時間が60分と短いため、時間配分が重要です。
- 対策:
- 読解問題:
- 多様なテーマの長文読解問題に取り組みましょう。特に環境、生物、科学といった「理系」分野の英文を重点的に演習することが効果的です。
- 指示語や代名詞、繰り返し出てくる表現とその言い換え表現、抽象的表現とその具体例などを意識して、文単位の理解を深め、パラグラフごとの大意を掴む練習をしましょう。これは内容真偽や主題、内容説明問題に有効です。
- 文章のつながりを意識し、単語・熟語の知識をしっかり身につけながら、意味のわからない単語を前後から類推する練習を積んでおきましょう。
- 文中の前置詞や不定詞などの意味・用法といった基本的な文法知識を特に力を入れて学習してください。
- 出題英文の語数が増加傾向にあるため、1000語を超える文章を集中して一気に読み切る練習をしておくと良いでしょう。その際は、パラグラフごとの要旨を考えつつも、常に全体の流れの一部であることを意識することが大切です。
- 文法・語彙問題:
- 2023-2025年度は大問での文法・語彙問題の出題がありませんでしたが、今後出題される可能性も考慮し、しっかりと対策しておきましょう。
- 文法や語法は全ての英語力の基礎となるため、出題形式にとらわれずに身につけることが重要です。特に標準的な文法力は、長い英文を正確に解釈する力となり、読解問題を解く上で大きな助けとなります。
- 時制、分詞、仮定法など多岐にわたる文法項目が出題される可能性があるため、やや難しめの文法・語法問題集をこなしておくと良いでしょう。
- 読解問題:
- おすすめ問題集:
- 『医歯薬系の英単語』(テーマの分類と重要語の整理に役立つ)
- 『長文読解・英作文のための実を結ぶ英文法(標準問題編・発展問題編)』(自信をつけるのに役立つ)
数学
- 傾向:
- 2025年度の出題範囲は「数学I,II,III,A(図形の性質・場合の数と確率),B(数列,統計的な推測),C(ベクトル、平面上の曲線と複素数平面)」です。
- 大問4題構成で、試験時間は100分。全問マークシート式による空所補充形式です。
- 融合問題が多く、広範囲から出題しようという意図が見られます。
- 微・積分法、確率は毎年出題されています。
- 標準的な頻出問題が中心ですが、計算力を要する問題がほとんどであり、難しく感じられることがあります。
- 問題量も多いため、試験時間内に全問を解答するには、確実な計算力が必要不可欠です。解法の見通しが良い問題から解いていくなど、時間配分にも気を配る必要があります。
- 対策:
- 基本事項の徹底学習: 標準的な問題が中心なので、基礎学力の充実が最も大切です。教科書や参考書の頻出重要例題を繰り返し解き、解法パターンをしっかり身につけるようにしましょう。
- 計算力の養成: 毎年かなりの計算力を要する問題が出題されるため、計算力の養成が欠かせません。日頃から計算を面倒がらずに、実際に手を動かして最後までやり通す習慣をつけましょう。解答だけが要求されている場合、要領よく計算することで時間短縮につながるため、計算の簡略化を図る練習もしておくと良いです。指数・対数・三角関数などを含んだ微分・積分の計算力もつけておく必要があります。
- 空所補充形式対策: 空所補充形式の問題集で解答の仕方に慣れることが大切です。赤本を利用して、過去問の練習をしっかり積んでください。微・積分法や確率、場合の数については、共通テストの過去問も活用すると有効です。空所補充形式での計算ミスは致命的となるため、具体的な数値などによって短時間に解答を点検できるよう、十分な練習をしておくこと。時間不足で解ける問題に手をつけられない状況を避けるためにも、時間配分を意識した演習を積んでおきましょう。
- おすすめ問題集:
- 『青チャート』
- 『Focus Gold』
- 学校で購入した問題集
- 赤本(過去問)
- 共通テストの過去問(微・積分法や確率、場合の数)
化学
- 傾向:
- 出題範囲は「化学基礎、化学」です。
- 大問数は4題で、試験時間は80分。全問マークシート式で、解答群から適当な語句などを選択する形式と、計算結果の数値を1桁ごとにマークする形式が中心です。
- 幅広い分野から出題されていますが、理論化学・有機化学分野が重視される傾向にあります。特に理論全般、異性体、天然有機化合物はよく出題されます。
- 総合的な学力を問うため、1つの問題の中に多くの知識・理論を組み込んで幅広く問うものもあります。
- 理論は無機や有機との融合問題も多いです。過去には環境問題に関連した出題もありました。
- 無機の出題は比較的少ないですが、2023年度以降は大問でも出題されています。各論的知識を要するものが多いです。
- 有機は、実験結果や実験過程を示して、反応や生成物、分子式、異性体、構造式、識別法などを問う問題が出題され、幅広い有機の知識と、有機化合物の性質や反応についての十分な理解が必要です。
- 近年では、核酸の構造やDNAの塩基対に関する問題も出題されており、油脂、タンパク質、糖類、ATP、核酸など生命と科学に関する内容に注意が必要です。
- 計算は典型的なものが多く、難解なものは比較的少ないです。
- 内容的にはやや難しい問題が含まれることもあり、問題量も多いため、時間配分に注意が必要です。
- 対策:
- 基礎を確実にし、幅広い知識を習得する: 総合的に様々な形で出題されるため、断片的な知識だけでは解けない問題もあります。まず、教科書の全範囲にわたって基本的な内容を確実に整理・理解し、それから数多くの問題に当たるようにしましょう。
- 理論: 熱化学、中和滴定、酸化還元反応、電池、電気分解、化学結合と物質の状態、気体の性質、溶解度、希薄溶液の性質、反応速度、化学平衡など、いずれの分野も出題されています。どの分野が出題されても得点できるように、学校で配布される傍用問題集や発展的な問題集を利用して、幅広く練習しておくことが重要です。
- 無機: 出題は比較的少ないですが、気体の製法・捕集法、無機化合物の工業的製法、陽イオンの分析、錯イオンの生成といった各論的内容は、実験と合わせて学習しておきましょう。実験操作の方法・意味、及び実験結果の理論的考察についても学習が必要です。
- 有機: 天然有機化合物の出題頻度が高いので、構造・反応などを中心に詳細な内容まで学習しておくこと。有機化学の基本問題を十分に練習し、総合・融合問題に備えましょう。元素分析、分子量測定から組成式・分子式の決定、官能基の性質、炭素間結合の特性、反応過程を通しての構造式の決定、異性体の種類などの一連の問題や、有機反応の名称・種類・反応式などを十分に学習し、有機化学特有の思考力を養っておくことが求められます。実験操作に関しては、器具名・操作法を暗記するだけでなく、操作の意味を一つ一つ考えることも大切です。
- 計算: 理論、無機、有機のいずれの内容にも計算問題が出題されますが、標準的なものが多いです。典型的な計算問題を十分に練習し、正確に計算する習慣を身につけることが重要です。選択肢の中から近い数値を選ぶ問題もあるため、検算しやすいように計算過程をきっちりと書き、正確性を高めましょう。
- おすすめ問題集:
- 学校で配布される傍用問題集
- 『実践 化学重要問題集 化学基礎・化学』
合格最低点
2024年度入試における薬学部の合格最低点は以下の通りです。
- 薬学科
- 一般B方式: 209点/300点
- グローバル方式: 268点/325点
- 共テA方式: 644点/800点
- 共テC方式併用: 388点/500点
- 生命創薬科学科
- 一般B方式: 203点/300点
- グローバル方式: 238点/325点
- 共テA方式: 644点/800点
- 共テC方式併用: 388点/500点
これらのデータは2024年度入試の結果に基づくものであり、入試情報は必ず募集要項等で最終確認してください。
英語外部資格・検定試験の活用
東京理科大学薬学部では、外部英語資格・検定試験のスコアを入試で活用できる制度があります。
- グローバル方式: 出願資格として英語資格・検定試験のスコアが求められ、さらに個別試験の総合点に加点優遇の対象となります。
- 加点対象となる英検CSEスコア、TEAP、TEAP CBT、IELTSの基準が示されています(例:英検CSE 3300で加点25点、1400で出願可能)。英検の受験級は問われません。
- A方式(2教科+英語資格検定): 外部英語資格・検定試験のスコアが基準を満たせば出願可能です。事前に所定スコアを取得することで、他の受験科目の勉強に集中できるメリットがあります。
- 総合型選抜(英語資格検定+特定教科評価): こちらも出願に英語資格検定のスコアが求められます。
英語の資格を持っていると、入試で有利になるだけでなく、大学入学後の学習や将来のキャリアにも役立つため、早めの取得をおすすめします。
東京理科大学薬学部に向いている高校生像
東京理科大学薬学部は、薬剤師や薬学研究者を目指す学生にとって非常に魅力的な環境です。以下のような特徴を持つ高校生は、特にこの学部に適していると言えるでしょう。
- 理系科目の基礎学力がしっかりしている人: 入試科目の傾向からもわかるように、数学、化学、物理/生物といった理系科目の基礎が徹底されていることが求められます。特に、論理的な思考力や計算力が重要です。
- 粘り強く学習に取り組める人: 薬学の学びは多岐にわたり、専門知識の習得には地道な努力が必要です。また、入試問題も計算量が多く、読解量も増加傾向にあるため、粘り強く問題に取り組む姿勢が求められます。
- 知的好奇心旺盛で、探求心がある人: 「創薬科学」や「生命薬学」といった研究分野に興味を持ち、自ら課題を見つけて解決しようとする探求心がある学生は、生命創薬科学科で世界をリードする研究者を目指す上で非常に向いています。
- 医療や公衆衛生に貢献したいという強い意欲を持つ人: 薬学科では、医療現場や公衆衛生における実践能力を重視した教育が行われます。人々の健康や社会に貢献したいという明確な目標を持つ学生にとっては、最適な学びの場となるでしょう。
- 論理的思考力と問題解決能力を養いたい人: 薬学の分野では、病気のメカニズムの解明や新しい薬の開発、患者への適切な薬物指導など、常に論理的な思考と問題解決能力が求められます。これらの能力を大学で高めたいと考える高校生にはおすすめです。
- 英語学習に意欲的な人: 英語外部資格・検定試験の活用が推奨されており、英語力は入試だけでなく、最新の薬学研究論文を読む上でも必須となります。英語の学習を苦にせず、むしろ積極的に取り組める人は有利です。
高校1年生・2年生・3年生からの受験対策のコツ
東京理科大学薬学部の合格を掴むためには、高校生活全体を通じた計画的な学習が重要です。
高校1・2年生のうちにすべきこと
- 基礎学力の徹底:
- 数学と化学を中心に、教科書の内容を完璧に理解することに努めましょう。特に、公式の暗記だけでなく、その導出過程や意味を理解することが大切です。
- 理系科目については、学校で配布される傍用問題集や標準レベルの参考書を繰り返し解き、基礎的な解法パターンを身につけ、計算力を地道に養いましょう。計算は毎日少しずつでも良いので、手を動かして練習する習慣をつけることが重要です。
- 英語の基礎固め: 単語、熟語、文法の基礎を固めます。特に文法は、長文読解の正確な理解に不可欠です。早い段階で英検®などの外部英語資格・検定試験に挑戦し、スコアアップを目指すのも良いでしょう。
- 多様な分野に興味を持つ: 薬学は生物、化学、物理、数学など様々な分野と関連しています。幅広い分野に興味を持ち、知識を深めることで、将来の学習にも役立ちます。
高校3年生で総仕上げ!
- 入試傾向に合わせた実践的な演習:
- これまでの基礎固めをベースに、過去問演習を本格的に開始しましょう。過去問を解くことで、出題形式や時間配分の感覚を掴むことができます。
- 時間配分を意識した演習: 特に英語や化学、数学では問題量が多い傾向にあるため、時間内に解き切る練習が重要です。解法の見通しが良い問題から着手するなど、効率的な解答戦略を練りましょう。
- 苦手分野の徹底克服: 過去問演習や模試の結果から、自身の弱点となっている分野を特定し、集中的に学習して克服しましょう。
- 記述力・論述力の強化(総合型選抜対策): 総合型選抜を考えている場合は、書類作成、面接、小論文の対策も並行して行いましょう。自分の考えを論理的に表現する練習を重ねることが重要です。
経済的なサポートも充実!奨学金制度
東京理科大学では、学生が安心して学べるよう、複数の奨学金制度を用意しています。
- 【給付】【予約採用型】新生のいぶき奨学金
- 給付額: 年額80万円~40万円(高等教育の修学支援新制度との併給の場合、支援区分に応じた金額を別途設定)。
- 給付期間: 4年間(薬学科は6年間)※年次継続審査あり。
- 採用人員: 300名程度。
- 応募条件: 一般選抜(理学部第二部を除く)、学校推薦型選抜、総合型選抜を受験して入学を希望する者で、父母と居住する実家から入学希望の学部・学科の所属するキャンパスへ通学することが困難であり、家計支持者の収入・所得金額の条件を満たす者。
- 申込時期および方法: 7月、8月~9月、11月~12月(一般選抜のみ)に学生支援課(神楽坂)へ申し込みます。入試選抜前に採用候補者が発表されます。
- 他制度併用: 乾坤の真理奨学金(BS)との併用は不可です。
- 【給付】乾坤の真理奨学金(BS)
- 給付額: 年額80万円~40万円。
- 給付期間: 4年間(薬学部は6年間)※年次継続審査あり。
- 採用人員: 規定による。
- 採用条件: 一般選抜AまたはB方式を受験して入学する成績優秀者(理学部第二部を除く)。新入生が対象です。
- 他制度併用: 新生のいぶき奨学金との併用は不可です。
これらの奨学金は、経済的な負担を軽減し、学業に専念できる環境をサポートしてくれます。詳細は学生支援部学生支援課(TEL 03-5228-8127)にお問い合わせください。
卒業後の進路とキャリア
東京理科大学薬学部を卒業した後の進路は多岐にわたります。薬剤師として医療現場で活躍する道もあれば、研究者として新薬開発に貢献する道もあります。
主な就職先
2023年4月~2024年3月卒業者の進路データによると、薬学部の卒業者80名中、72名が就職し、6名が進学しています(薬学科)。生命創薬科学科では、卒業者79名中、4名が就職し、74名が進学しています。これは、生命創薬科学科が研究者養成を目的としているため、大学院進学率が高いことを示しています。
薬学部の主な就職先としては、以下のような企業や医療機関が挙げられます。
- アインホールディングス
- 日本調剤
- 日本新薬
- 協和キリン
- 東京大学医学部附属病院
- ファイザー
- 第一三共
- クオール
- イオンリテール
- IQVIAサービシーズジャパン
- 日本イーライリリー
これらの情報から、調剤薬局、製薬会社、病院など、多様な分野で活躍していることがわかります。
取得可能な資格
東京理科大学薬学部薬学科を卒業すると、薬剤師の国家試験受験資格が得られます。薬剤師は、患者への薬の説明や調剤、医薬品の管理など、医療の最前線で重要な役割を担う専門職です。
研究室・研究内容の展望
薬学科(6年制)は、薬剤師としての実践能力と問題解決能力に加え、問題を研究に結びつける能力を兼ね備えた人材の育成を目指しています。これは、単に薬を使うだけでなく、臨床現場で生じる課題を科学的に分析し、研究を通じて解決策を探る能力が求められていることを示唆しています。
生命創薬科学科(4年制)は、高度な専門知識と技能を備え、世界をリードできる優れた薬学研究者の養成を目標としています。ここでは、「創薬科学」と「生命薬学」という2つの主要な研究分野があります。
- 創薬科学: 従来の創薬手法に加え、ゲノム情報などの最先端の理論的アプローチを活用し、新しい医薬品の創出を目指します。
- 生命薬学: 生命の営みを多角的に探求し、病気の発生メカニズムを解明することで、より効果的な医薬品の開発に繋げます。
東京理科大学薬学部は、学内だけでなく国内外の様々な医療系大学、研究機関、企業と連携した共同研究・教育を推進しています。これにより、学生は最先端の研究に触れる機会が多く、多様な視点から薬学の課題に取り組むことができます。卒業後は、大学院に進学してさらに研究を深め、製薬会社や研究機関で新薬開発や基礎研究に従事するなど、薬学研究の未来を担う人材として活躍することが期待されます。
まとめ
東京理科大学薬学部は、その確かな歴史と「実力主義」の教育方針のもと、未来の医療と薬学研究を牽引する人材を育成するための最適な環境を提供しています。2025年の葛飾キャンパスへの移転により、さらに学びやすい環境が整うでしょう。
高い偏差値と共通テスト得点率、そして競争率の高い入試を突破するためには、数学、化学、英語といった主要科目の基礎を徹底し、計算力や読解力を磨き、計画的に過去問演習に取り組むことが不可欠です。特に、数学と化学の計算力、英語の長文読解力は、合格への鍵となるでしょう。また、外部英語資格・検定試験の活用は、入試における有利な要素となり得ます。
学費は決して安くはありませんが、成績優秀者や経済的支援が必要な学生向けの充実した奨学金制度も用意されており、安心して学業に専念できるサポート体制が整っています。
薬剤師としての専門性と人間性を高めたい方、あるいは最先端の薬学研究に携わり、新しい医薬品の開発を通じて社会に貢献したいという強い意欲を持つ高校生にとって、東京理科大学薬学部は理想的な選択肢となるはずです。
このブログ記事が、皆さんの志望校選びと受験対策の一助となれば幸いです。東京理科大学薬学部で、皆さんの夢を現実にする一歩を踏み出してください!応援しています!
薬学部 を本気で目指すあなたへ!
薬学部受験専門塾PharmAssistは、全国初の薬学部受験に特化した専門塾です。
- 「どの大学を受けるべきか分からない」
- 「何から勉強を始めればいいか不安」
- 「このままの勉強法で合格できるのか心配」
そんな悩みを持つ高校生・浪人生・保護者の皆さまへ、無料の個別受験相談を実施中です!
🎁 今だけ、LINE登録で『薬学部合格ロードマップ』を無料プレゼント中!
📲 受験戦略・学習計画・志望校対策まで、すべてLINEで気軽にご相談いただけます。
📩 薬学部合格を本気で目指すなら、今すぐご相談ください!
PharmAssistでは、薬学部志望者向けに無料の受験相談・体験授業を実施中!
LINE登録で、個別勉強計画+教材アドバイスも無料でプレゼント中!
無料体験授業で、志望薬学部合格のための戦略を作成!
薬学部合格を目指すなら、PharmAssistで今の実力と志望校のギャップを見える化しませんか?
無料体験授業で、あなた専用の学習計画・受験計画表をお渡しします!
当塾では、志望大学・薬学部に合格するために、最善の学習方法を、生徒一人ひとりに合わせて提供しております。
薬学部に合格したいという高校生の皆さん。
絶対に後悔のしない大学受験を保証します。
ぜひ、当塾、薬学部受験専門塾PharmAssist(ファーマシスト)で1週間の無料体験授業を受けていただき、
ご縁がございましたら、ご入会していただけることを心待ちにしています。
ファーマシストは高校生の薬学部受験を専門としたオンライン塾です。
今月の定員は残り3名です‼︎‼︎
すぐに定員に達することが予想されますので、お早めに公式LINEからお問い合わせください。
体験授業につきましても、
以下の画像をタップして友達登録をお願いします。
登録後、「〇〇コースの体験を受けてみる!」をタップしてお問い合わせください。
薬学部受験専門塾 PharmAssist(ファーマシスト)
代表 寺沼香太朗